見逃していませんか?訪問看護で出会うフレイルのサインと実践的対応法
「最近、田中さんの歩く速度が遅くなった気がする…」 「前は一人でお風呂に入れていたのに、最近は介助が必要になってきた」 「体重が減っているけど、これって病気?それとも年だから?」
訪問看護の現場で、こんな風に感じたことはありませんか?利用者さんの「なんとなく弱くなった」という変化に気づきながらも、それが自然な老化なのか、何か対応が必要な状態なのか判断に迷うことがあると思います。
実は、その「なんとなく」の変化こそが、フレイルという重要な状態を示しているかもしれません。
定義
フレイルは「虚弱」を意味する英語「Frailty」が語源で、健康と要介護の中間的な状態を指します。多くの人が「年を取れば弱くなるのは当然」と考えがちですが、実はここに大きな落とし穴があります。
フレイルを見過ごすと起こること:
-
転倒・骨折のリスクが急激に高まる
-
感染症にかかりやすくなり、重症化しやすくなる
-
入院をきっかけに一気に要介護度が上がる
-
認知機能の低下が加速する
つまり、「ちょっと弱くなっただけ」と思っていた状態を放置すると、利用者さんの生活の質が大幅に低下し、私たち訪問看護師の支援も後手に回ってしまうのです。
体験談
私は訪問看護師として5年間働く中で、多くの利用者さんのフレイル状態に関わってきました。特に印象に残っているのは、85歳のAさんのケースです。
Aさんは最初「ちょっと足腰が弱くなっただけ」と訪問を開始しましたが、フレイルの兆候を早期に発見し、多職種で連携して対応した結果、1年後には自分で買い物に行けるまでに改善されました。
一方で、同じような状況でフレイルのサインを見逃してしまった利用者さんは、半年後に転倒・骨折で入院し、要介護度が一気に上がってしまったケースもありました。
厚生労働省のデータによると、フレイルの高齢者は健常な高齢者と比べて要介護認定を受けるリスクが約2.4倍、死亡リスクが約2.6倍高くなることが分かっています。だからこそ、私たち訪問看護師がフレイルを理解し、適切に対応することが利用者さんの人生を大きく左右するのです。
ポイント5選
ポイント1:フレイルの5つの診断基準を覚えよう
フレイルの診断には、以下の5つの基準が使われます:
1. 体重減少:6ヶ月で2-3kg以上の意図しない体重減少 2. 疲労感:「わけもなく疲れた感じがする」が週3-4日以上 3. 活動量低下:軽い運動・体操を週1回もしていない 4. 歩行速度低下:横断歩道を青信号で渡りきれない 5. 握力低下:男性28kg未満、女性18kg未満
具体例: Aさん(78歳女性)の場合、訪問時に「最近、買い物袋を持つのがつらくて…」という訴えがありました。握力を測定すると16kg(基準値以下)、さらに聞き取りをすると「この半年で服がゆるくなった」「疲れやすくて外出が億劫」という症状も。結果、3項目に該当し、フレイルと判定されました。
一言アドバイス: 全ての項目を毎回チェックする必要はありません。日常の観察の中で「あれ?」と思った変化があったら、関連する項目を意識的に確認してみましょう。
ポイント2:身体・心理・社会の3つの側面から観察する
フレイルは単なる身体機能の低下ではありません。以下の3つの側面から包括的に捉える必要があります:
身体的フレイル
-
筋力・筋肉量の減少
-
栄養状態の悪化
-
慢性疾患の影響
精神・心理的フレイル
-
うつ傾向
-
不安の増大
-
意欲の低下
社会的フレイル
-
社会とのつながりの減少
-
経済的困窮
-
家族関係の変化
具体例: Bさん(82歳男性)は、妻を亡くしてから「食事を作るのが面倒」「誰とも話さない日が続く」という状態でした。体重減少と活動量低下に加え、社会的孤立とうつ傾向が見られ、3つの側面すべてでフレイルの兆候がありました。
一言アドバイス: 「今日は元気がないな」と感じたら、身体面だけでなく「最近、お友達と会ってる?」「心配事はない?」といった声かけで、心理・社会面の変化もキャッチしましょう。
ポイント3:栄養状態の簡易チェック法を活用する
フレイルの予防・改善において、栄養は極めて重要な要素です。訪問現場で使える簡単なチェック法をご紹介します:
MNA-SF(簡易栄養状態評価表)の活用
-
食事摂取量の変化
-
体重減少の有無
-
運動機能
-
精神的ストレス・急性疾患の経験
-
神経・精神的問題
-
BMI
現場での観察ポイント:
-
冷蔵庫の中身(期限切れ食品、偏った食材)
-
食事の準備状況
-
食べ残しの様子
-
水分摂取量
具体例: Cさん(79歳女性)の冷蔵庫を確認すると、おかずは総菜パンとカップ麺ばかり。「料理が面倒になって…」という話から、栄養不足によるフレイル進行が判明しました。管理栄養士と連携し、簡単な栄養補助食品の導入と配食サービスの利用で改善につながりました。
一言アドバイス: 栄養指導は専門職に任せがちですが、訪問看護師だからこそ見える「食べる環境」の情報は貴重です。気づいたことは積極的に多職種と共有しましょう。
ポイント4:運動機能維持のための実践的アプローチ
フレイル対策において運動は薬と同じくらい重要ですが、訪問現場で実践しやすい方法を選ぶことが大切です。
在宅でできる簡単な運動プログラム:
1. 椅子を使った筋力トレーニング
-
椅子からの立ち上がり(1日10回×3セット)
-
椅子に座ったままの足上げ(片足10回×3セット)
2. バランス訓練
-
片足立ち(左右各30秒、転倒防止のため壁や椅子を支えに)
-
歩行時のかかと・つま先歩き
3. 有酸素運動
-
室内での足踏み運動
-
天気の良い日の散歩(15-30分)
具体例: Dさん(76歳男性)は膝痛のため運動を敬遠していましたが、椅子を使った運動から開始し、3ヶ月で歩行速度が改善。「運動って大変だと思っていたけど、これなら続けられる」と前向きになられました。
一言アドバイス: 利用者さんの身体状況や住環境に合わせて、無理なく続けられる運動を提案することが成功の鍵です。「完璧」より「継続」を重視しましょう。
ポイント5:多職種連携でのフレイル対応戦略
フレイルの改善には、チームアプローチが不可欠です。訪問看護師としてどのように多職種と連携するかが重要になります。
連携のポイント:
主治医との連携
-
フレイルの兆候発見時の報告
-
基礎疾患の管理状況確認
-
薬剤調整の必要性検討
理学療法士との連携
-
運動機能評価の実施
-
個別運動プログラムの作成
-
福祉用具の検討
管理栄養士との連携
-
栄養状態の評価
-
食事指導・栄養補助の検討
ケアマネジャーとの連携
-
サービス内容の見直し
-
社会資源の活用検討
具体例: Eさん(83歳女性)のケースでは、私がフレイルの兆候を発見後、主治医に報告し血液検査で栄養状態を確認、理学療法士による運動機能評価、管理栄養士による食事指導を経て、ケアマネジャーが通所リハビリの追加を調整。3ヶ月で明らかな改善が見られました。
一言アドバイス: 「気になることがある」段階での早めの情報共有が、効果的な介入につながります。完全な情報がそろってからではなく、「予兆」の段階で相談することを心がけましょう。
よくある質問
Q1:フレイルと認知症の区別がつかない場合はどうする?
A: フレイルと認知症は併発することも多く、区別が難しい場合があります。重要なのは「どちらか」を決めることではなく、両方の可能性を考慮したアプローチをとることです。
認知機能検査(HDS-RやMMSE)と並行して、身体機能の評価も行い、主治医と情報を共有しましょう。
Q2:家族が「年だから仕方ない」と理解してくれない
A: 家族への説明では、「予防できる老化」と「自然な老化」は違うことを丁寧に伝えます。
「確かに年を取れば体は変化しますが、適切なケアで改善できる部分も多いんです。実際に○○さんのような方が改善された例もあります」といった具体例を交えると理解が得られやすくなります。
Q3:本人に運動や食事改善の意欲がない場合は?
A: 無理強いは逆効果です。まずは小さな成功体験を積み重ねることから始めましょう。
例えば「今日は調子が良さそうですね。ちょっと一緒に歩いてみませんか?」といった声かけで、自然に活動量を増やすきっかけを作ります。本人の「できた!」という実感が次のステップへのモチベーションになります。
注意点:見落としやすいフレイルのサイン
-
薬の飲み忘れが増える:認知機能低下の可能性も含めて評価
-
以前好きだった活動をやめる:うつ傾向の可能性
-
「疲れた」が口癖になる:単なる愚痴ではなく、フレイルのサイン
-
電話の声が小さくなる:全身の筋力低下の表れの可能性
まとめ
フレイルは「気づき」から始まります。今回ご紹介したポイントを振り返ると:
1. 5つの診断基準を意識した観察 2. 身体・心理・社会の3つの側面からの評価 3. 栄養状態の簡易チェック 4. 実践的な運動アプローチ 5. 多職種連携での包括的支援
明日からの訪問で、利用者さんの「ちょっとした変化」に今まで以上に注意を向けてみてください。その「気づき」が、利用者さんの人生の質を大きく変える第一歩になるかもしれません。
今すぐできるアクション:
-
今担当している利用者さんの中で、フレイルの兆候がないか振り返ってみる
-
チームメンバーとフレイルについて情報共有してみる
-
次の訪問時に、いつもより少し踏み込んで生活状況を観察してみる
フレイルは「可逆性」つまり改善可能な状態です。私たち訪問看護師の「気づき」と「行動」が、利用者さんの未来を変える力になります。一緒に頑張りましょう!
このような図解もあってわかりやすい本1冊あれば在宅の現場では役に立ちます。特に家族へのアドバイスなどに有効です!
是非ご購読を!
最後まで読んでいただきありがとうございました。

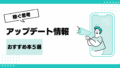
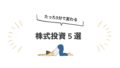
コメント