「利用者さんにどう接すればいいのかわからない…」 「介護技術は習ったけど、実際の現場では思うようにいかない」 「先輩に聞きたいことがあるけど、忙しそうで声をかけにくい」
介護の仕事を始めて間もない頃、こんな風に感じたことはありませんか?教科書や研修で学んだことと、実際の現場で求められることの間にあるギャップに戸惑う気持ち、とてもよくわかります。
利用者一人ひとりの個性や状況が違う中で、「正解」が見えないまま日々の業務に追われ、「本当にこれでいいのだろうか」と不安になることもあるでしょう。
しかし、この「なんとなく」の状態を放置していると、思わぬ落とし穴が待っています。
適切な知識やスキルがないまま介護を続けていると、利用者の状態を悪化させてしまったり、自分自身が燃え尽きてしまったりするリスクがあります。また、自己流の介護方法が身についてしまうと、後から正しい方法を学び直すのに倍の時間がかかってしまうことも。
「経験を積めばなんとかなる」と思いがちですが、基礎となる知識と理論を持たずに経験だけを積んでも、真の成長にはつながりません。むしろ、間違った習慣を強化してしまう危険性すらあるのです。
私の体験
私は介護業界で7年以上働き、新人介護士の指導も数多く経験してきました。その中で気づいたのは、「本当に利用者に寄り添える介護士」と「なんとなく業務をこなしている介護士」の間には、決定的な違いがあるということです。
その違いの一つが、「学び続ける姿勢」でした。優秀な介護士ほど、常に新しい知識を吸収し、自分の介護観を更新し続けています。実際、私が指導した新人スタッフの中でも、積極的に書籍から学んでいた人たちは、わずか半年で見違えるような成長を遂げていました。
厚生労働省の調査でも、継続的な学習を行っている介護職員の離職率は、そうでない職員と比べて約30%低いという結果が出ています。知識と技術に裏打ちされた自信は、仕事への満足度を大きく向上させるのです。
介護初心者におすすめ本5選
それでは、介護士として確実にステップアップできる、厳選した5冊をご紹介します。
1. 『ユマニチュード入門』(本田美和子・イヴ・ジネスト・ロゼット・マレスコッティ著)
なぜおすすめか: ユマニチュードは「人間らしさを取り戻すケア技術」として世界中で注目されている手法です。認知症の方との関わり方に悩んでいる介護士には特に効果的です。
具体例: 例えば、「見る・話す・触れる・立つ」という4つの基本技術を使って、攻撃的になりがちな利用者との関係を劇的に改善できます。実際に私の職場でも、この技術を導入後、利用者の表情が明らかに穏やかになりました。
一言アドバイス: まずは「見る」技術から始めてみてください。正面から目を見て話しかけるだけで、利用者との信頼関係は大きく変わります。
2. 『介護職のための医学知識』(長尾和宏著)
なぜおすすめか: 介護と医療は密接に関わっているため、基本的な医学知識は介護士にとって必須です。この本は医師が介護職向けに分かりやすく書いた一冊です。
具体例: 利用者の「いつもと違う様子」に気づけるかどうかが、重大な疾患の早期発見につながることがあります。血圧や脈拍の正常値を知っているだけで、看護師や医師への報告の質が格段に向上します。
一言アドバイス: すべてを覚える必要はありません。「これは注意すべきサイン」という感覚を養うことから始めましょう。
3. 『認知症ケアの基本』(川畑智著)
なぜおすすめか: 認知症の方への対応は、介護現場で最も難しい課題の一つです。この本は認知症の症状を理解し、適切な関わり方を学べる実践的な内容です。
具体例: 「帰りたい」と訴える利用者に「ここがあなたの家ですよ」と説得するのではなく、その気持ちを受け止めながら別の方向に意識を向ける技術など、具体的な対応方法が豊富に紹介されています。
一言アドバイス: 認知症の方の行動には必ず理由があります。まずはその理由を理解しようとする姿勢が大切です。
4. 『移乗・移動の介護技術』(福祉技術研究会編)
なぜおすすめか: 正しい介護技術を身につけることで、利用者の安全を守り、自分の身体も守ることができます。写真やイラストが豊富で、実践的な内容です。
具体例: ボディメカニクスの原理を理解することで、小柄な女性でも大柄な利用者を安全に移乗させることが可能になります。腰痛予防にも直結する重要な技術です。
一言アドバイス: 一人で練習せず、必ず同僚と一緒に練習して、正しい姿勢を身につけましょう。
5. 『介護職のためのコミュニケーション術』(岡田慎一郎著)
なぜおすすめか: 技術や知識だけでなく、利用者やその家族、同僚との良好な関係を築くコミュニケーション能力は介護士にとって不可欠です。
具体例: 「傾聴」の技術を身につけることで、利用者の本当のニーズを理解できるようになります。また、家族への報告の仕方一つで、信頼関係は大きく変わります。
一言アドバイス: 相手の立場に立って考える習慣を身につけることから始めてみてください。
よくある質問
Q: 忙しくて読書の時間が取れません… A: 一日15分でも構いません。休憩時間や通勤時間を活用してください。音声読み上げアプリを使うのも効果的です。
Q: 本を読んでも実際に活かせるか不安です A: 完璧を目指す必要はありません。一つでも「これは使える!」と思った技術を実践してみてください。小さな変化の積み重ねが大きな成長につながります。
Q: どの本から読み始めればいいですか? A: 今最も困っている問題に関連する本から始めることをおすすめします。例えば、認知症の利用者への対応に悩んでいるなら『認知症ケアの基本』から始めてください。
注意点: 本で学んだ知識は、必ず職場の先輩や上司に確認してから実践するようにしましょう。施設によってルールや方針が異なる場合があります。
まとめ
介護の仕事に正解はありませんが、より良いケアを提供するための「指針」は確実に存在します。今回ご紹介した5冊は、その指針を見つけるための強力なツールとなるでしょう。
今回僕が特におすすめするのがこの本です。
この本でケアの概念が変わりました。
介護初心者でもわかりやすく説明されているのでおすすめの本です。
是非ご購読を!!

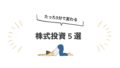
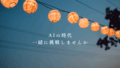
コメント