「おじいちゃんの最期は、住み慣れた自宅で迎えさせてあげたい」
そう思いながらも、心の中では様々な不安が渦巻いているのではないでしょうか。
「本当に家で看取れるのだろうか」 「急変したときに対応できるだろうか」 「家族だけで大丈夫なのだろうか」 「痛がっているのに何もできなかったらどうしよう」
訪問看護師として働く私のもとにも、このような相談が数多く寄せられます。また、同じ職場の新人看護師からも「在宅での看取りに立ち会うのが初めてで不安です」という声をよく聞きます。
あなたの気持ち、とてもよくわかります。大切な人の最期に関わることだからこそ、不安になるのは当然なのです。
しかし、この「不安」をそのままにしておくと、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。
多くの方が見落としがちなのは、在宅看取りは「家族だけで頑張るもの」ではないということです。実際に、準備不足や情報不足のまま在宅看取りを始めてしまい、
-
急変時にパニックになって救急車を呼んでしまった
-
本人の苦痛を取り除けずに後悔が残った
-
家族の負担が想像以上に重く、共倒れ状態になった
-
医療者との連携がうまくいかず、孤立してしまった
このような状況に陥ってしまうケースを何度も目にしてきました。
「なんとかなる」という気持ちだけでは、本人にとっても家族にとっても、満足のいく看取りは実現できないのが現実です。
体験談
私は訪問看護師として5年間、200名以上の方の在宅看取りに携わってきました。がん終末期の方、高齢による衰弱の方、神経難病の方など、様々な疾患の方の最期に立ち会わせていただいています。
また、厚生労働省の調査によると、自宅で亡くなる方の割合は約13%程度ですが、「最期は自宅で過ごしたい」と希望する方は約60%にのぼります。つまり、多くの方の希望が叶えられていないのが現状なのです。
この現状を変えたい、そして一人でも多くの方に満足のいく在宅看取りを経験していただきたいという思いから、今回実体験に基づいた具体的なアドバイスをお伝えします。
在宅で看取る際の5つのポイント
ポイント1:医療チームとの事前の話し合いを徹底する
理由: 在宅看取りでは、医師、看護師、ケアマネジャー、薬剤師など多職種との連携が不可欠です。事前の準備不足は、いざというときの混乱を招きます。
具体例: 80代の男性のケースでは、家族と医療チーム全員で「急変時の対応方針」「痛みが強くなった場合の対処法」「最期の瞬間に誰に連絡するか」を事前に詳細に決めていました。そのおかげで、実際の看取りの際も家族は落ち着いて対応でき、本人も穏やかに最期を迎えることができました。
一言アドバイス: 恥ずかしがらずに「こんなことを聞いてもいいのかな」と思う質問もすべて医療者に確認してください。準備の段階で不安を解消することが、安心な看取りにつながります。
ポイント2:家族の役割分担と休息の確保を計画する
理由: 看取りは数日から数週間に及ぶことが多く、家族が24時間つきっきりでは心身ともに疲弊してしまいます。持続可能な体制作りが重要です。
具体例: ある家庭では、三人の子どもたちが「日中担当」「夜間担当」「買い物・事務手続き担当」に分かれ、さらに訪問介護サービスも活用することで、誰も無理をせずに看取りを行うことができました。
一言アドバイス: 「自分たちだけで頑張らなければ」という思い込みは捨ててください。利用できる社会資源はすべて活用し、家族も体調を崩さないよう配慮することが、結果的に本人のためにもなります。
ポイント3:症状変化の目安と対応方法を習得する
理由: 在宅では医療者がそばにいない時間が長いため、家族が症状の変化に気づき、適切な初期対応ができることが重要です。
具体例: 呼吸が浅くなる、手足が冷たくなる、意識レベルが下がるなどの変化について、事前に医師から説明を受けていた家族は「これは自然な経過なんだ」と理解し、慌てることなく本人に寄り添うことができました。
一言アドバイス: 医療者から説明を受けた内容は、家族全員で共有しメモに残しておきましょう。不安になったときに見返すことで、冷静さを取り戻すことができます。
ポイント4:本人の意思と価値観を確認し尊重する
理由: 看取りの主役はあくまで本人です。家族の思いも大切ですが、本人がどのような最期を望んでいるかを知り、それを尊重することが何より重要です。
具体例: 90代の女性は「最期まで好きな音楽を聴いていたい」「孫の顔を見ていたい」という希望を表していました。家族がその希望を叶えられるよう環境を整えた結果、本人も満足した表情で旅立たれました。
一言アドバイス: 意識がはっきりしているうちに、本人の希望や価値観について話し合う時間を持ちましょう。それが看取りの方向性を決める大切な指針となります。
ポイント5:事後の悲嘆ケアも含めた準備をする
理由: 看取りは終了ではなく、その後の家族の悲嘆プロセスも含めて考える必要があります。事前に心の準備をしておくことで、健康的な悲嘆を経験できます。
具体例: 看取り後に家族が「もっとできることがあったのではないか」と後悔することがないよう、看取りの過程で家族が行った愛情深いケアを医療者が言葉にして伝え続けました。
一言アドバイス: 看取り後も定期的に医療者や相談できる人とつながりを持ち続けることをおすすめします。悲しみは一人で抱え込まず、分かち合うことが大切です。
よくある質問
Q: 在宅看取りにはどのくらいの費用がかかるのでしょうか? A: 医療保険・介護保険が適用されるため、病院での治療と比べて大幅に負担が軽減されることが多いです。ただし、家族の負担軽減のための介護サービス利用などで追加費用が発生する場合もあります。
Q: 急に容態が悪化した場合はどうすればよいですか? A: まずは24時間対応の訪問看護ステーションや主治医に連絡を取ります。事前に緊急時の連絡先と対応手順を確認し、家族全員で共有しておくことが重要です。
Q: 訪問看護師として初めて看取りに関わる場合の心構えは? A: 完璧を目指さず、本人と家族に寄り添う姿勢を大切にしてください。わからないことは先輩に相談し、チーム全体で看取りを支えるという意識を持つことが大切です。
注意点: 在宅看取りは決して「医療の放棄」ではありません。積極的な治療から緩和ケア中心の医療へと方針を転換し、本人の苦痛を最小限に抑えながら、最期まで人としての尊厳を保つことを目指すものです。
まとめ
在宅看取りを成功させるための5つのポイントをお伝えしました:
-
医療チームとの事前の話し合いを徹底する
-
家族の役割分担と休息の確保を計画する
-
症状変化の目安と対応方法を習得する
-
本人の意思と価値観を確認し尊重する
-
事後の悲嘆ケアも含めた準備をする
在宅看取りは確かに不安を伴いますが、適切な準備と医療チームとの連携があれば、本人にとっても家族にとっても満足のいく最期を迎えることができます。
「最期は住み慣れた家で」という願いを叶えるために、まずは主治医や地域の訪問看護ステーションに相談することから始めてみてください。あなたと大切な方が、安心して在宅看取りに臨めるよう応援しています。
訪問看護師になって初めての看取りをする際に読んだ1冊です。
特に新人訪問看護師さんにおすすめの1冊となっています。
是非読んでみてください。

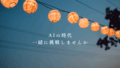
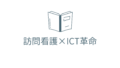
コメント