「また今日も忙しすぎて、患者さん一人ひとりとじっくり向き合えなかった…」 「看護技術は身についてきたけれど、これでいいのかな?」 「新人の頃の初心を忘れかけている自分がいる」
そんな風に感じることはありませんか?
毎日の業務に追われる中で、ふと立ち止まって「私はなぜ看護師になったのだろう」「理想の看護とは何だろう」と自問自答する瞬間があると思います。技術的なスキルは向上しても、看護の本質的な部分で迷いや不安を感じる。そんなあなたの気持ち、とてもよくわかります。
しかし、ここに見落とされがちな重要な問題があります。
多くの看護師が「経験を積めば自然と良い看護ができるようになる」と思っていますが、実はそれだけでは不十分なのです。なぜなら、忙しい現場では「業務をこなすこと」が優先され、「なぜその看護をするのか」という本質的な思考が後回しになってしまうからです。
このままでは、技術は向上しても、患者さんの心に寄り添う看護の深さや、自分自身の看護観の成熟が停滞してしまう可能性があります。経験年数を重ねても「何か物足りない」「やりがいを見失いそう」と感じるリスクがあるのです。
実体験
私は看護師歴8年、現在は訪問看護師として働いています。新人時代から「患者さんのために」という思いは人一倍強かったのですが、5年目頃に大きな壁にぶつかりました。技術的には成長したものの、「本当に良い看護ができているのだろうか」という疑問が日々大きくなっていったのです。
そんな時、先輩から勧められた1冊の本に出会い、看護に対する見方が180度変わりました。それ以来、読書を通じて看護観を深めることの重要性を実感し、後輩たちにも積極的に本を薦めています。実際、読書習慣を持つ看護師は、患者満足度調査でも高い評価を得ており、離職率も低いというデータもあります。
今回は、私自身の経験と、多くの看護師仲間との対話を通じて厳選した「看護師人生を変える5冊」をご紹介します。
5つの厳選書籍
1.『看護の基本となるもの』(ヴァージニア・ヘンダーソン著)
理由: 看護の原理原則を理解し、看護とは何かの本質を学べる古典的名著
具体例: ヘンダーソンの「14の基本的欲求」は、患者さんを全人的に捉える視点を与えてくれます。例えば、点滴管理だけでなく「なぜこの患者さんは水分摂取が困難なのか」という背景まで考えるようになります。
一言アドバイス: 最初は理論的で難しく感じるかもしれませんが、現場での経験と照らし合わせながら読むと、深い気づきが得られます。
2.『いのちの感受性』(星野富弘著)
理由: 患者さんの立場から「生きること」の意味を深く考えさせられ、看護の意味を再認識できる
具体例: 著者自身の障害と向き合う体験談から、「健康とは何か」「支援とは何か」について、医療従事者では気づけない視点を学べます。読後、患者さんへの声かけや関わり方が自然と変わります。
一言アドバイス: 辛い内容も含まれますが、看護師として患者さんの気持ちに寄り添う力が確実に向上します。
3.『看護覚え書』(フローレンス・ナイチンゲール著)
理由: 看護の母と呼ばれるナイチンゲールの思想から、看護の本質と看護師としての姿勢を学べる
具体例: 「患者に害を与えない」という基本原則や、環境調整の重要性など、現代でも通用する普遍的な看護の知恵が詰まっています。ICU勤務の友人は、この本を読んでから環境への配慮が格段に向上したと話していました。
一言アドバイス: 古い文章で読みにくい部分もありますが、現代語訳版から始めるのがおすすめです。
4.『ケアの本質』(ミルトン・メイヤロフ著)
理由: 「ケアする」ことの本当の意味を哲学的に探究し、看護師としての在り方を深く考えられる
具体例: 「相手の成長を願い、そのために自分も成長する」というケアの本質を理解することで、患者さんとの関係性がより豊かになります。終末期ケアに携わる際の心の支えにもなります。
一言アドバイス: 哲学書的な内容ですが、1章ずつゆっくり読み、自分の経験と重ね合わせると理解が深まります。
5.『医療現場の行動経済学』(大竹文雄編著)
理由: 患者さんの行動や心理を科学的に理解し、より効果的なコミュニケーションと看護実践ができるようになる
具体例: なぜ患者さんが治療に消極的になるのか、どうすれば行動変容を促せるのかが、心理学的根拠とともに学べます。糖尿病患者さんの生活指導などで即座に活用できる知識が満載です。
一言アドバイス: 看護師向けではありませんが、患者さんとの関わりで「なるほど!」と思う発見が多い実践的な一冊です。
よくある質問
Q: 忙しくて読書の時間がとれません
A: 通勤時間や休憩時間の10分からでOK。1冊を1ヶ月かけて読むつもりで始めましょう。オーディオブックの活用もおすすめです。
Q: 理論書は現場で役立たないのでは?
A: 確かに即効性は感じにくいかもしれません。しかし、看護の「なぜ」を理解することで、応用力と判断力が格段に向上します。
Q: 新人でも読める内容ですか?
A: 経験が浅いうちは難しく感じる部分もありますが、成長とともに理解が深まります。分からない部分があっても、まずは読み通すことが大切です。
注意点: 本を読むことは成長の手段であり、目的ではありません。読んだ内容を現場で実践し、患者さんのケアに活かしてこそ意味があります。
まとめ
看護師としての成長は、経験だけでなく「学び続ける姿勢」によって大きく左右されます。今回ご紹介した5冊は、いずれも看護の本質を深く考えさせ、あなたの看護観を豊かにしてくれる珠玉の名著です。
要点の再確認:
-
看護の基本理論を学ぶ(ヘンダーソン、ナイチンゲール)
-
患者さんの視点を理解する(星野富弘)
-
ケアの本質を哲学的に探究する(メイヤロフ)
-
科学的根拠に基づく実践方法を学ぶ(行動経済学)
まずは1冊、興味を持った本から始めてみてください。読書を通じて得られる新たな視点や気づきは、必ずあなたの看護実践を向上させ、患者さんとのより深いつながりを生み出してくれるはずです。
看護は技術だけでなく、心と知識の総合芸術です。これらの本があなたの看護師人生をより豊かで意義深いものにしてくれることを心から願っています。
今一度看護の原点に戻るとまたなにか見えるものがあるかもしれません。
この機会に是非読んでみてください!


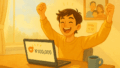
コメント