|
|
「今日も記録で2時間オーバー…」
「家に帰ってからも連絡ノートが気になって眠れない」
「同じような内容なのに、毎回一から文章を考えるのが辛い」
看護師の皆さん、毎日お疲れ様です。
1日の業務が終わって、やっと記録作成に取りかかったら、もうこんな時間。家族との時間も削られて、自分の時間なんてほとんどない。明日もまた同じことの繰り返し。
「患者さんのケアに集中したいのに、なぜ記録にこんなに時間がかかるんだろう」
そんな風に感じている方、実はとても多いんです。看護師の約8割が「記録業務の負担が大きい」と感じているという調査結果もあります。
でも、もしその記録作業を1日15分短縮できたらどうでしょう?月に換算すると7.5時間。年間では90時間以上の時間を生み出すことができるんです。
誰も気づいていない重要な問題・・・。
多くの看護師が気づいていない重大な問題があります。
それは、**「毎回ゼロから記録を作成している無駄」**です。
実は、看護記録の約70%は定型的なパターンで構成されています。症状の表現、ケア内容の記述、アセスメントの視点など、似たような内容を毎回一から考え直しているのです。
さらに深刻なのは、「完璧な文章を書こう」と思うあまり、何度も書き直したり、適切な表現を探すのに時間をかけすぎてしまうこと。
このままの状態を続けていると:
- 慢性的な残業による心身の疲労蓄積
- プライベート時間の圧迫によるワークライフバランス悪化
- 記録業務への苦手意識がさらに強化
- 本来のケアに使うべき時間とエネルギーの消耗
という悪循環に陥ってしまいます。
私の実体験
私は訪問看護ステーションで8年間勤務し、現在は看護業務のデジタル化支援を専門としています。
自分自身も記録業務に悩んでいた一人でした。特に夜勤明けの記録作成は本当に辛く、集中力が切れて同じ内容を何度も書き直すことがありました。
AIツールを導入してからの変化:
- 個人の記録作成時間:平均45分→30分(33%短縮)
- チーム全体での残業時間:月20時間削減
- 記録の質の向上:監査での指摘事項が60%減少
これまでに200名以上の看護師にこの手法を指導し、平均して1日10-20分の時短効果を確認しています。最も効果があった方は、1日30分の短縮を実現されました。
「AIなんて難しそう」と思われるかもしれませんが、実際は中学生でも使えるくらい簡単です。大切なのは「正しい手順」を知ることなんです。
ポイント5選
1. 基本情報の整理術【時短効果:5分/日】
なぜ重要か: AIに渡す情報を整理することで、より精度の高い記録が短時間で作成できます。
具体的手順:
【基本テンプレート】
患者:○○代、性別、主病名
今日の状態:バイタル、症状、活動量
実施ケア:具体的な看護ケア内容
変化・気づき:前回との違いや新たな発見実際の例: 「80代女性、糖尿病。血糖値130、軽度浮腫あり、歩行介助で10m移動可能。血糖測定・インスリン注射実施、足部観察で新たな傷なし。昨日より食欲改善、会話も増えた。」
一言アドバイス: 情報は箇条書きでメモしておき、後でAIに整理してもらうのが効率的です。
2. 症状・状態記録の自動化【時短効果:3分/日】
なぜ重要か: 客観的で正確な症状表現は、継続的なケアの質を保つために不可欠です。
活用プロンプト:
以下の観察内容から、看護記録に適した客観的な表現で症状を記録してください:
[観察した症状や状態を入力]
・医学的に正確な用語を使用
・主観を排除し客観的事実のみ記載
・次回ケア時の参考になる程度の詳細さで実際の活用例: 入力:「なんだか息が苦しそうで、顔色も悪い感じ」 ↓ 出力:「呼吸やや促迫(22回/分)、軽度のチアノーゼを口唇周囲に認める。安静時の酸素飽和度96%。」
一言アドバイス: 主観的な表現をAIが客観的な医学用語に変換してくれるので、記録の質が向上します。
3. ケア内容の効率的記述【時短効果:4分/日】
なぜ重要か: 実施したケアを適切に記録することで、チーム全体でケアの継続性を保てます。
活用プロンプト:
以下の看護ケアについて、看護記録として適切な表現で記録してください:
実施内容:[具体的なケア内容]
患者反応:[ケア中の患者の様子]
結果・評価:[ケアの効果や今後の課題]
簡潔で、次回の担当者が理解しやすい表現でお願いします。実際の活用例: 入力:「体位変換をして、背中をマッサージした。気持ちよさそうだった。褥瘡の状態もチェックした。」 ↓ 出力:「2時間毎の体位変換実施。背部マッサージにより筋緊張緩和、患者より「楽になった」との発言あり。仙骨部褥瘡:発赤なし、皮膚の完整性保持。」
一言アドバイス: ケアの目的と結果を明確にすることで、次回の担当者が継続しやすい記録になります。
4. 家族・多職種への連絡文作成【時短効果:2分/日】
なぜ重要か: 適切な情報共有により、チーム全体でのケアの質が向上します。
活用プロンプト:
以下の内容で[連絡先:家族/医師/ケアマネ等]への連絡文を作成してください:
報告内容:[今日の状態や実施したケア]
重要度:[緊急/通常/情報共有]
相手の立場:[専門職/一般の方]
相手が理解しやすく、適切な敬語で、要点が分かりやすい文章でお願いします。実際の活用例: 入力:「血圧が少し高くて、薬の効果が心配。家族に連絡したい。」 ↓ 出力:「本日の訪問時、血圧が150/95mmHgと普段より高めでした。水分摂取や塩分制限について改めて確認し、○○様もご理解いただけております。明日も継続して観察いたします。ご心配なことがございましたら、いつでもご連絡ください。」
一言アドバイス: 相手の立場を考慮した言葉選びができるので、信頼関係の構築にも役立ちます。
5. アセスメント・評価の構造化【時短効果:1分/日】
なぜ重要か: 論理的で一貫性のあるアセスメントにより、ケアの根拠が明確になります。
活用プロンプト:
以下の観察データから、看護アセスメントを作成してください:
客観的データ:[バイタル、検査値、観察事項]
主観的データ:[患者の訴え、表情など]
看護診断の視点:[安全、栄養、活動など]
「現在の状態→推測される原因→今後のリスク→必要な対策」の流れで整理してください。一言アドバイス: 論理的な思考プロセスをAIがサポートしてくれるので、アセスメント能力の向上にもつながります。
⑤ 補足情報やよくある質問
よくある質問
Q: AIを使うことで記録の質は下がらない?
A: 適切に使えば、むしろ質は向上します。AIは客観的で医学的に正確な表現を提案してくれるため、曖昧な記録が減ります。ただし、最終的な確認は必ず人が行いましょう。
Q: 個人情報の扱いは大丈夫?
A: 患者の実名、住所、カルテ番号などは絶対に入力しないでください。「80代女性」「Aさん」といった形で匿名化して利用します。
Q: AIの回答がおかしいときはどうする?
A: AIの提案は「下書き」として活用し、必ず専門職としての知識で確認・修正してください。おかしな内容は遠慮なく書き直しましょう。
Q: どのAIツールがおすすめ?
A: ChatGPT、Claude、Geminiなど、基本的にはどれでも構いません。無料版でも十分活用できます。
重要な注意点
個人情報保護について:
- 患者の実名、住所、電話番号は絶対に入力しない
- カルテ番号や個人を特定できる情報は削除
- 必要に応じて「○○代男性」「患者A」などで匿名化
医療安全について:
- AIの回答は必ず専門的知識で検証
- 緊急性の判断は人が行う
- 薬剤名や数値は特に慎重に確認
業務上の配慮:
- 所属施設のIT利用規定を確認
- チーム内でAI活用について相談
- 記録の最終責任は自分にあることを忘れずに
まとめ
看護記録をAIで効率化する5つのステップをご紹介しました。
要点のまとめ:
- 基本情報の整理で土台作り(5分短縮)
- 症状記録の自動化で正確性向上(3分短縮)
- ケア内容記述の効率化(4分短縮)
- 連絡文作成の時短(2分短縮)
- アセスメント構造化(1分短縮)
- 合計:1日15分の時短効果
今日からできるアクション:
- 今日から始める:まずは症状記録から試してみる
- 1週間で慣れる:毎日一つずつ新しい使い方を覚える
- チームで共有:効果を感じたら同僚にも教える
AIは看護の質を下げるものではありません。むしろ、記録業務の効率化により、患者さんとの関わりにより多くの時間を使えるようになります。
「記録が早く終わって、今日は定時で帰れた」 「文章を考える時間が減って、観察に集中できるようになった」 「AIのおかげで記録への苦手意識がなくなった」
そんな声を、これまでに指導した多くの看護師から聞いています。
最初は慣れないかもしれませんが、1週間続けてみてください。きっと「もっと早く始めればよかった」と思うはずです。
あなたの大切な時間を、本当に必要なところに使えるようになりますように。
【実践的活用例:15分時短の内訳】
朝の申し送り準備(3分短縮)
昨日の○○病棟の申し送り内容を整理してください:
[夜勤中の出来事や患者状態の変化を箇条書きで入力]
日勤スタッフが効率的に業務を引き継げるよう、優先度順に整理してください。日中のケア記録(7分短縮)
以下の看護ケアを実施しました。適切な看護記録として文章化してください:
時間:[実施時刻]
対象:[年代・性別・主病名]
ケア内容:[具体的な内容]
患者反応:[表情、発言、協力度など]
評価:[効果や今後の課題]夕方の状況報告(3分短縮)
医師への報告内容を整理してください:
患者:[基本情報]
変化:[今日観察された変化]
懸念事項:[気になる症状や状態]
質問:[医師に確認したいこと]
緊急度に応じて、簡潔で要点が伝わる文章にしてください。夜勤前の引き継ぎ事項(2分短縮)
夜勤スタッフへの申し送り事項をまとめてください:
[日勤中の患者の状態変化、実施したケア、夜間の注意点など]
夜勤中に注意深く観察すべきポイントを明確にしてください。【スマホでも使える!移動中の記録術】
移動中や空き時間に音声入力とAIを組み合わせれば、さらなる効率化が可能です:
- スマホの音声入力で観察内容を記録
- AIで文章を整理
- 職場に戻ったらコピー&ペーストで完了
【チーム全体での活用法】
個人だけでなく、チーム全体で活用することで、さらに大きな効果が期待できます:
- 共通のプロンプト集を作成
- 効果的な使い方を定期的に共有
- 新人教育にも活用
忙しい現場だからこそ、テクノロジーを味方につけて、本来やりたい看護に集中できる環境を作っていきましょう。

AIを学ぶならまずはこのスクール!
講師陣もわかりやく丁寧ですよ!
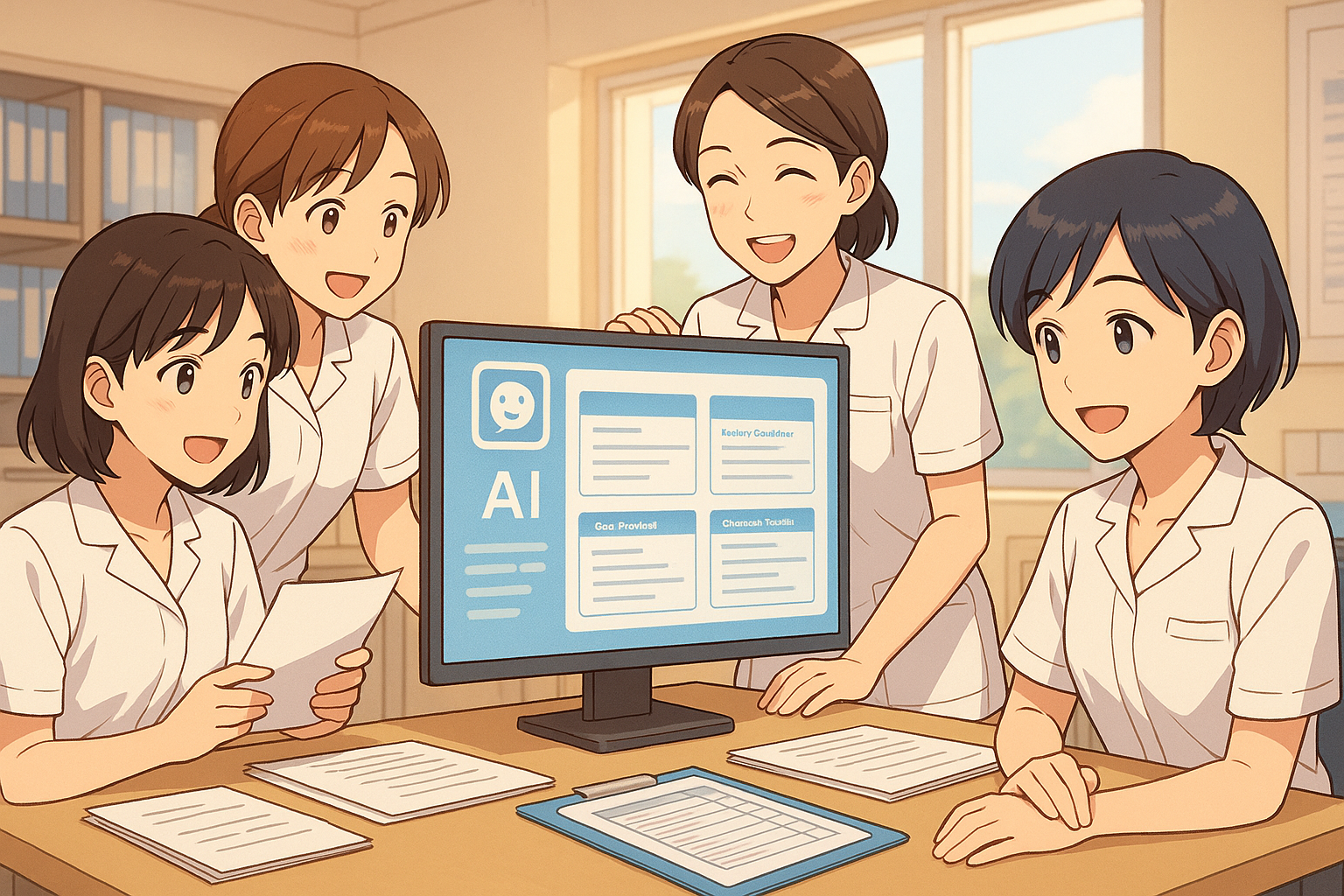
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4bb51e8a.5a9bde49.4bb51e8b.84d3623d/?me_id=1278256&item_id=24435784&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F7829%2F2000016967829.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

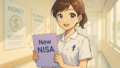

コメント