「指示書の記載内容がよくわからない…」
「緊急時にどこに連絡すればいいかわからない…」
「多職種連携って具体的にどうすればいいの?」
訪問看護の現場で、こんな悩みを抱えていませんか?
病院勤務から訪問看護に転職した方、新人看護師として訪問看護をスタートした方、そしてベテランでも「これで合ってるのかな?」と不安に感じる場面は必ずあります。
特に一人で利用者宅を訪問する訪問看護では、その場で判断を迫られる場面が多く、「これって緊急?」「指示書の範囲内?」「誰に相談すべき?」といった疑問が次々と湧いてきます。
実は、訪問看護における「指示書」「連携」「緊急対応」の理解不足は、単なる知識不足の問題だけではありません。
見落とされがちな3つの落とし穴
- 指示書の解釈を間違えて、必要なケアができない
- 連携不足により利用者の状態変化を見逃す
- 緊急時の判断ミスで、適切なタイミングを逃す
これらの問題は、利用者の生命に直結する重大なリスクです。特に訪問看護では、その場で適切な判断ができなければ、取り返しのつかない事態に発展する可能性があります。
「なんとなく」「たぶん大丈夫」という曖昧な理解のままでは、いつか必ず壁にぶつかってしまいます。
実体験
私は訪問看護ステーションで管理者として8年間、200名以上の利用者のケアに携わってきました。新人看護師の指導から、複雑な医療処置が必要な利用者のケアまで、現場の最前線で様々な課題と向き合ってきました。
これまでに経験した実例
- 指示書の解釈違いで、必要な処置が1週間遅れたケース
- 連携不足により、利用者の状態悪化を早期発見できなかったケース
- 緊急時の連絡体制が整っておらず、適切な対応が遅れたケース
これらの経験から学んだのは、「現場でよくある疑問」には必ずパターンがあり、事前に準備しておけば適切に対応できるということです。
今回は、実際に現場で頻繁に遭遇する50の質問を厳選し、それぞれに具体的な解決策をお答えします。
【指示書関連】よくある質問TOP15
Q1: 指示書に記載のない処置を求められた場合の対応は?
A: 必ず主治医に確認を取ってください。口頭指示の場合は、指示を受けた看護師名・日時・指示内容を記録し、後日指示書の追記を依頼します。
Q2: 指示書の有効期限が切れそうな時の対応は?
A: 期限の1週間前には主治医に更新を依頼。緊急時は電話で確認し、後日書面で確認を取ります。
Q3: 家族から「前の看護師さんはやってくれた」と言われた場合は?
A: 指示書を再確認し、記載がない場合は「安全のため主治医に確認させてください」と説明。家族の不安に共感しつつ、医療安全の重要性を伝えます。
Q4: 複数の医師から異なる指示が出された場合の優先順位は?
A: 主治医の指示を最優先とし、専門医の指示がある場合は主治医に情報共有して調整を依頼します。
Q5: 指示書の内容が曖昧で判断に迷う場合は?
A: 具体的な疑問点をリスト化し、主治医に確認。「〇〇の場合はどうするか」という形で具体的に質問することが重要です。
【多職種連携】よくある質問TOP20
Q6: ケアマネジャーとの連携で最も重要なポイントは?
A: 利用者の状態変化を迅速に共有すること。特に医療面での変化は24時間以内に報告し、ケアプランの見直しが必要か判断してもらいます。
Q7: 主治医との連携がうまくいかない場合の対処法は?
A: 連絡のタイミングと方法を確認。診療時間外の緊急連絡先、連絡の優先度の基準を事前に明確にしておきます。
Q8: 家族との意見が分かれた場合の調整方法は?
A: まず全員の意見を聞き、医学的見解を説明。ケアマネジャーや主治医を交えたカンファレンスの開催を提案します。
Q9: 他の訪問看護ステーションとの情報共有はどこまで?
A: 利用者の同意を得た範囲で、安全なケア提供に必要な医療情報を共有。個人情報保護に配慮しつつ、継続性を重視します。
Q10: リハビリ職種との連携で注意すべき点は?
A: ADLの変化や疼痛の有無など、互いの専門性を活かした情報交換。定期的な合同訪問で統一したアプローチを確認します。
【緊急対応】よくある質問TOP15
Q11: 緊急性の判断基準がわからない場合は?
A: バイタルサインの著明な変化、意識レベルの低下、呼吸困難、胸痛、重篤な転倒などは即座に対応。迷った場合は「緊急」として判断することが重要です。
Q12: 夜間・休日の緊急連絡体制はどう整備すべき?
A: 主治医、訪問看護ステーション、家族、救急搬送先の連絡先を一覧化。連絡優先順位と判断基準を明文化しておきます。
Q13: 救急搬送の判断に迷った場合の対応は?
A: 「#7119」(救急安心センター事業)を活用。医学的見地から適切な助言を受けられます。迷ったら搬送する方向で判断を。
Q14: 家族が救急搬送を拒否した場合の対応は?
A: 生命に危険がある場合は医療的必要性を説明し、主治医からも説明してもらいます。それでも拒否される場合は記録に残し、管理者に報告。
Q15: 緊急時の記録はどこまで詳細に書くべき
A: 5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を明確に記載。特に判断の根拠と対応の経過を時系列で詳しく記録します。
よくある誤解と注意点
誤解①:「指示書があれば何でもできる」 → 指示書の範囲内でも、利用者の状態に応じた個別判断が必要です。
誤解②:「緊急時は家族の意向を最優先すべき」
→ 医学的に必要な処置は、家族の理解を得ながらも医療者として適切に判断することが重要です。
誤解③:「連携は情報を伝えるだけ」 → 双方向のコミュニケーションと、継続的な情報更新が真の連携です。
法的な注意点
- 指示書なしでの医療処置は医師法違反になる可能性があります
- 緊急時であっても、可能な限り適切な手続きを踏むことが重要です
- 記録は法的証拠となるため、客観的事実を正確に記載してください
新人看護師への特別アドバイス
「わからないことは恥ずかしくない」という意識を持ちましょう。先輩看護師や管理者に相談することで、自分だけでなく利用者の安全も守れます。
まとめ
訪問看護における「指示書」「連携」「緊急対応」は、利用者の生命と生活の質に直結する重要な要素です。
今日から実践できる3つのアクション
- 指示書の見直し:担当利用者の指示書を再確認し、不明な点は主治医に質問リストを作成して確認する
- 連携体制の確認:各利用者の関係職種と連絡方法、緊急時の連絡先を整理してリスト化する
- 緊急対応の準備:緊急時の判断フローチャートを作成し、いつでも見られる場所に保管する
訪問看護の現場では、完璧を求めすぎず、「利用者にとって最善の選択は何か」を常に考えることが大切です。困ったときは一人で抱え込まず、チーム全体で支え合いながら、質の高いケアを提供していきましょう。
あなたの「困った」が「できた」に変わることで、利用者とその家族により良いケアを届けることができます。今日から一歩ずつ、確実に前進していきましょう。
この記事が少しでもお役に立てたら、ぜひシェアやいいねをお願いします。現場で頑張る訪問看護師さんたちの励みになります。
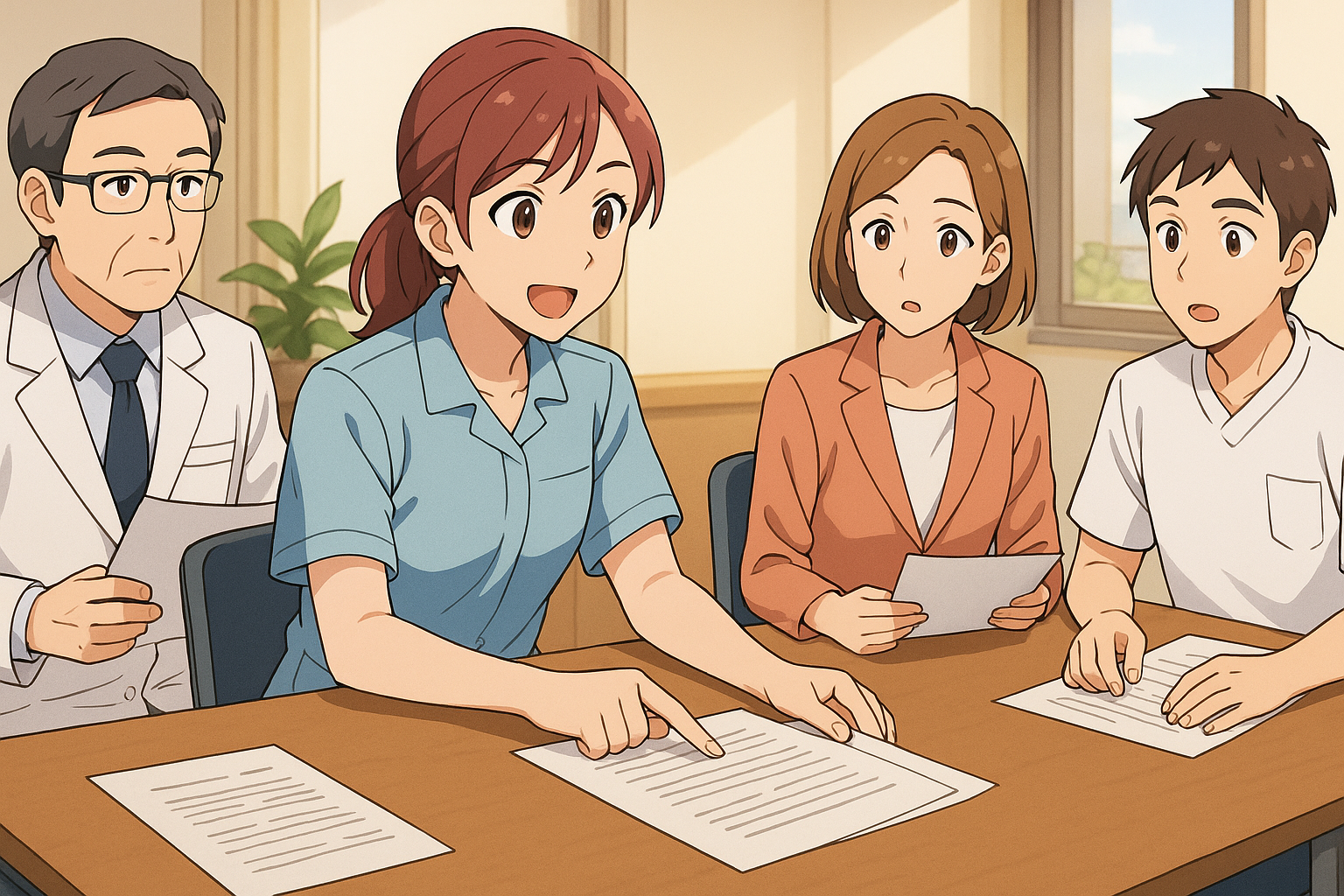


コメント