「最近、母が同じ話を何度も繰り返すようになった…」
「父が料理の段取りを忘れて、キッチンで立ち尽くしていることが増えた」 「買い物に行っても必要なものを忘れて帰ってくる」
こんな親の変化に気づいて、心のどこかで「もしかして認知症?」という不安を抱えていませんか?
でも、「まだ大丈夫」「年のせいだろう」と自分に言い聞かせて、現実と向き合うことを先延ばしにしてしまう。一方で、もし本当に認知症だったら、何から手をつければいいのか分からず、途方に暮れてしまう。
そんなあなたの気持ち、とてもよく分かります。実際に、私が訪問看護師として関わらせていただいた多くのご家族が、同じような悩みを抱えていらっしゃいました。
認知症の怖さは、症状の進行だけではありません。実は、「気づくのが遅れること」による二次的な問題の方が深刻なケースが多いのです。
例えば:
-
服薬管理ができなくなり、慢性疾患が悪化する
-
火の消し忘れや道に迷うなど、安全面でのリスクが高まる
-
本人の混乱や不安が増し、家族との関係がギクシャクする
-
介護保険の申請が遅れ、必要なサービスを受けられない
「様子を見ましょう」という期間が長引くほど、本人も家族も辛い思いを重ねることになります。早期発見・早期対応が、その後の生活の質を大きく左右するのです。
私の経験から
私は訪問看護師として8年間、認知症の方とそのご家族の支援に携わってきました。これまで約200世帯のお宅を訪問し、初期症状の段階から終末期まで、様々なケースを経験してきました。
その中で痛感するのは、初期症状を正しく理解し、適切なタイミングで専門機関につなげることの重要性です。早期に訪問看護や介護サービスを導入できたご家族は、その後も在宅での生活を長く継続できる傾向にあります。
厚生労働省の発表によると、65歳以上の高齢者の約6人に1人が認知症とされており、2025年には約700万人に達すると推計されています。決して他人事ではない現実なのです。
5つのサイン
1. 記憶の変化:「覚えていること」と「忘れること」のパターンに注目
なぜ重要か: 単なる物忘れと認知症による記憶障害には明確な違いがあります。健康な物忘れは「体験の一部」を忘れますが、認知症では「体験そのもの」を忘れてしまいます。
具体例:
-
健康な物忘れ:「昨日、誰と食事したっけ?」(食事したことは覚えている)
-
認知症の記憶障害:「昨日、食事をしましたか?」「していません」(食事したこと自体を忘れている)
一言アドバイス: 同じ質問を短時間で繰り返したり、最近の出来事を全く覚えていない場合は、早めに専門医に相談することをお勧めします。
2. 日常動作の変化:「できていたこと」ができなくなる兆候
なぜ重要か: 長年慣れ親しんだ家事や趣味ができなくなるのは、脳の実行機能に影響が出ている可能性があります。これは初期症状として現れやすい特徴の一つです。
具体例:
-
料理の手順が分からなくなる(調味料を入れる順番を忘れる、火加減が分からない)
-
家計簿がつけられなくなる、ATMの操作に時間がかかる
-
洗濯物の仕分けができない、掃除の段取りが立てられない
一言アドバイス: 「やり方を忘れた」ではなく「やろうとする気持ちがない」場合は、意欲の低下として別の原因も考えられるため、総合的な判断が必要です。
3. 時間・場所の感覚:見当識の変化を見逃さない
なぜ重要か: 時間や場所の感覚が曖昧になるのは、認知症の中核症状の一つです。日常生活に大きな支障をきたす前に気づくことが大切です。
具体例:
-
曜日や日付が分からなくなる(「今日は何曜日?」と頻繁に聞く)
-
慣れた道で迷う(近所のスーパーから帰れなくなった)
-
季節感がなくなる(真夏に厚いコートを着ようとする)
一言アドバイス: 外出時は常に連絡先を書いたメモを持参してもらい、GPS機能付きの見守りサービスの利用も検討しましょう。
4. コミュニケーションの変化:言葉と行動のちぐはぐさ
なぜ重要か: 言語機能の低下や理解力の変化は、本人の不安や混乱を増大させ、家族関係にも影響を与えます。早期に気づいて適切な対応を取ることで、コミュニケーション能力を長く維持できます。
具体例:
-
適切な言葉が出てこない(「あれ」「それ」などの指示語が増える)
-
話の筋道が通らなくなる(話題があちこちに飛ぶ)
-
読み書きが困難になる(新聞を読まなくなった、手紙が書けない)
一言アドバイス: 責めたり訂正したりせず、本人の気持ちに寄り添う姿勢を大切にしてください。「そうですね」と受け入れる対応が、関係性を保つコツです。
5. 性格・行動の変化:これまでとは違う一面の出現
なぜ重要か: 性格の変化や新しい行動パターンの出現は、家族が最も戸惑いを感じる部分です。これらが病気による症状であることを理解することで、適切な対応ができるようになります。
具体例:
-
疑い深くなる(「財布を盗られた」と家族を疑う)
-
怒りっぽくなる、または逆に無関心になる
-
同じ行動を繰り返す(何度も電話をかける、同じものを何個も買ってくる)
一言アドバイス: これらの行動には必ず理由があります。頭ごなしに否定せず、なぜそのような行動を取るのか、本人の立場に立って考えてみることが大切です。
よくある質問
Q: 「年のせいでしょう」と本人が病院に行くのを嫌がります
A: 無理に説得せず、まずは「健康チェック」や「薬の相談」など別の理由で受診を提案してみてください。かかりつけ医がいる場合は、事前に状況を相談しておくと良いでしょう。
Q: どのタイミングで専門医を受診すべきですか?
A: 上記の症状が複数当てはまり、日常生活に支障が出始めた段階が目安です。「様子を見る」期間は1〜2ヶ月程度に留め、改善がない場合は受診をお勧めします。
Q: 診断を受けた後、どのような支援が受けられますか?
A: 介護保険の申請、訪問看護・介護サービス、デイサービス、認知症カフェなど様々な選択肢があります。地域包括支援センターに相談すると、適切なサービスを紹介してもらえます。
注意点:
-
症状には個人差があり、すべてが認知症とは限りません
-
薬の副作用や他の病気が原因の場合もあります
-
早期発見のメリットを理解し、恐れずに専門機関に相談することが大切です
まとめ
認知症の初期症状は、日常生活の小さな変化として現れます。重要なのは以下の5つのポイントでした:
-
記憶の変化:体験そのものを忘れるパターンに注意
-
日常動作の変化:慣れた作業ができなくなる
-
時間・場所の感覚:見当識の混乱を見逃さない
-
コミュニケーションの変化:言葉と行動のちぐはぐさ
-
性格・行動の変化:これまでとは違う一面の出現
これらの症状に気づいたら、一人で抱え込まずに専門機関に相談してください。早期発見・早期対応により、本人らしい生活をより長く維持することができます。
今日からできること:
-
親の日常の変化を記録してみる
-
地域の相談窓口(地域包括支援センター)の連絡先を調べておく
-
家族で認知症について話し合う機会を作る
あなたとご家族が、穏やかな日々を過ごせますよう、心から応援しています。困ったときは、いつでも専門職に頼ってくださいね。
この本は図解などもあり、介護制度についても詳しく書かれています。
今不安な家族な方やこれから親の介護を待ち受けている現役世代の方たちにも読んで欲しい1冊となっています。
一度読んでみてくださいね!
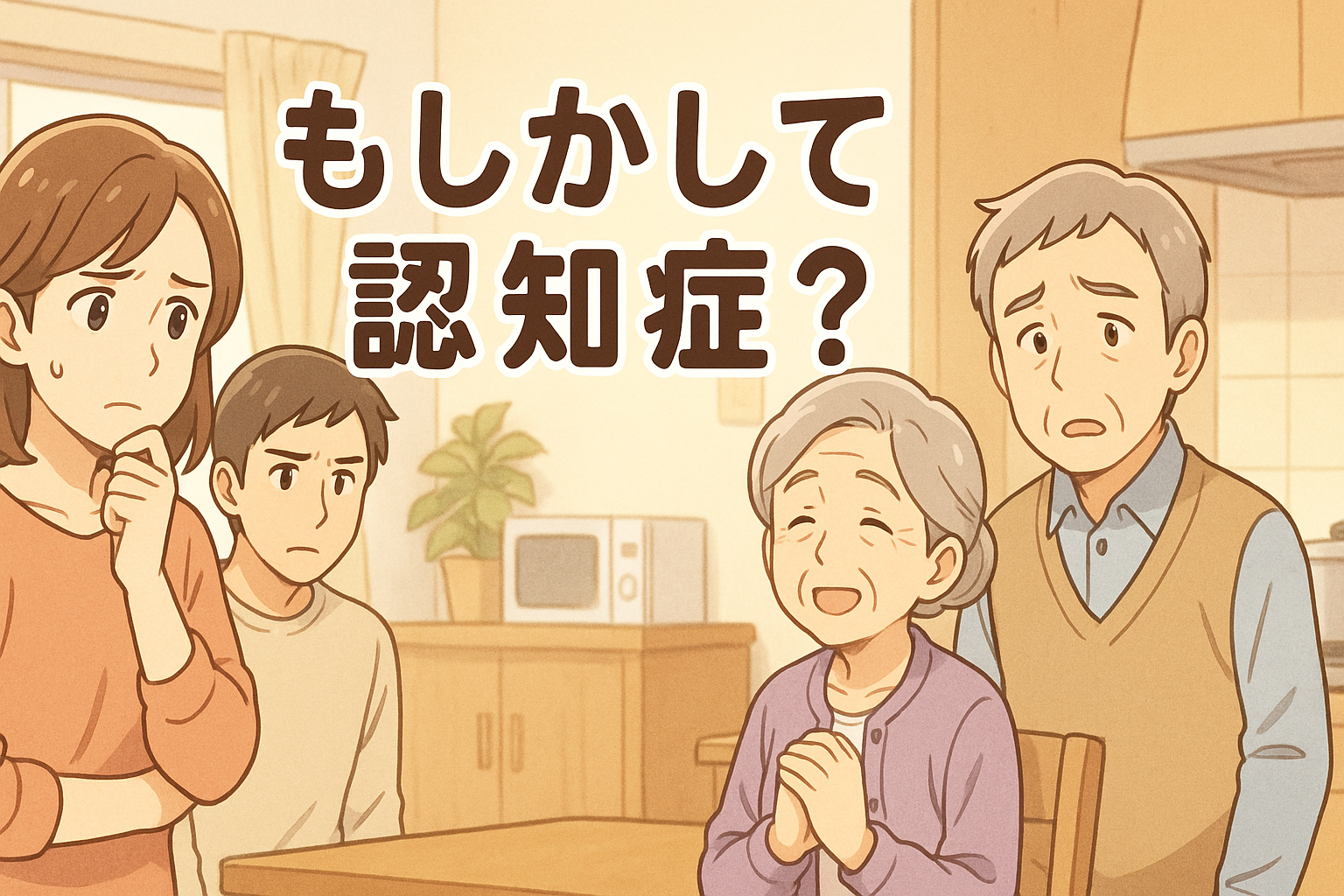

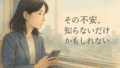
コメント